「富谷洋介建築設計」様の設計・監理の札幌市中央区S様邸では、鉄筋コンクリート造である基礎の鉄筋組を行いました。

文字通り、基礎は「鉄筋」と「コンクリート」による構造体です。 「現場で作る」物は、施工管理が必要となります。 その記録として、鉄筋組の全景を撮影しました。

鉄筋組の施工管理はとても難しく、管理すべき項目が多いです。 そして、住宅の基礎工事というのは、非常にテキパキと進むので、スピード感をもった工程管理(D)が必要とされます。


配筋完了は、工程管理(D)のキーデートとなるため、施工完了日をしっかりと押さえ、第三者機関と設計監理者による配筋検査も実施しています。 S様邸の配筋検査は問題なく「適合」となりました。

配筋の施工管理のもっとも基本的な事は、立ち上がりとベース鉄筋の径と間隔の確認です。


実は、私の現場では、この後、検査員と施工管理者(私)との技術者同士の細かいやり取りが、いつも始まります。 配筋の施工管理項目は非常に多く、ざっくりと説明すると、「鉄筋の製品(規格、材質)の確認」、「現場で組まれた鉄筋の間隔・配置・定着、重ね継手(ラップ)」、「被り厚さ(ベース底や両側、立ち上がりの両型枠までの距離)」、「開口部補強筋の配筋」、「コーナー補強筋の配筋」などで、実際現場では納まりが悪く、教科書通りには施工できないヶ所も出てきます。また、教科書である「建築基準法」の解釈も人それぞれであり、「現場で現物を見て現状を確認」してくれる人との時間は、私にとっては同じ目線で話せる数少ない機会なので、とても大切にしています。


2025年4月1日から、建築基準法が改正しました。 「省エネ」と「構造」に関して、現在にふさわしい内容に改正しています。 「鉄筋はフックにしなければ、ならない」という解釈も出てきているようです。 丸鋼なのか異形鉄筋なのかなど、さまざまな見解もあると思いますが、S様邸ではフックとしています。
木造住宅を「大工」という技術者が建てたのは千年以上も前であり、家は経験と勘で建て続けられてきた建築物です。 「今までの経験(職人)」と「現代の理論(公的機関・専門技術者・設計者)」の両方と仕事ができる、この施工管理者という職種に、今ではとても、やりがいを感じています。
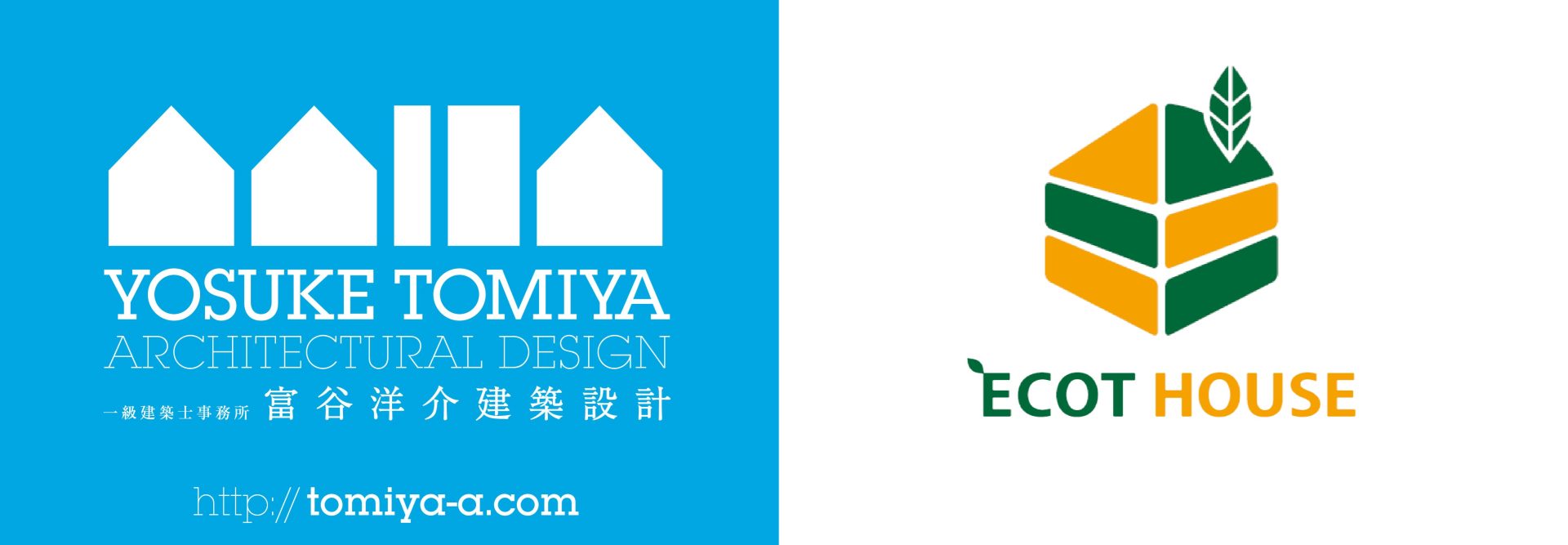
設計・監理→「富谷洋介建築設計」様のHP
個別現場レポート→「札幌市中央区S様邸」
